エアコンの除湿機能の正しい使い方はコレ!設定温度や風向きを解説
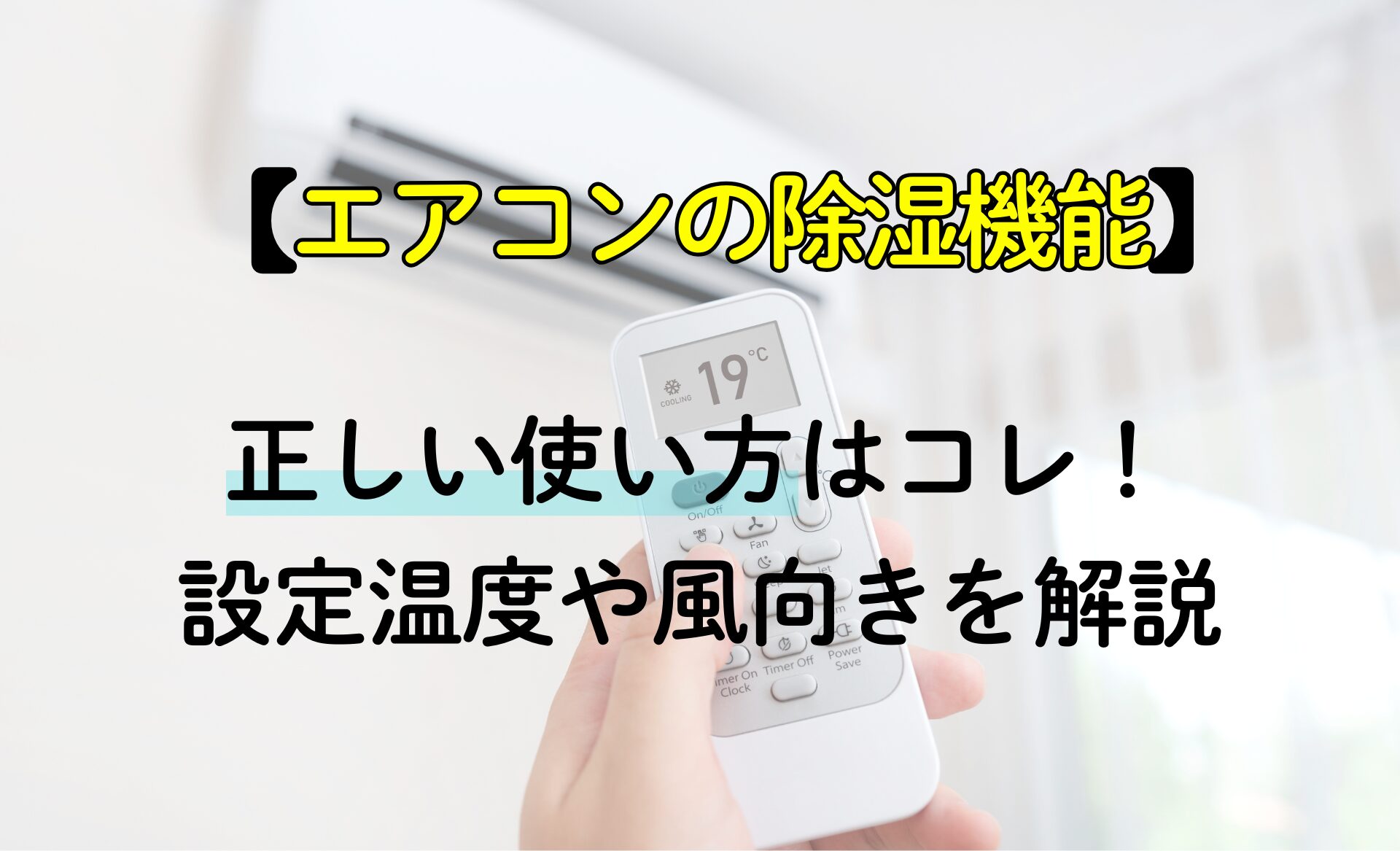
「エアコンの除湿機能、効いているのか分からない」
「風向きは、どんな設定が効果的なんだろう」
「風向きを調べてみたけど、いろんな答えがあって何が正しいか分からない」
とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
エアコンの除湿機能は、湿気を取り除き室内を涼しく快適に保ってくれます。
しかし、室内の環境に合った正しい使い方ができていないと、十分に効果を実感できない場合があります。
本記事では、ご自身のお悩みを解決する除湿機能の使い方を学べるよう、次のことを紹介します。
- エアコン除湿の基礎知識
- エアコン除湿を使うときの風向き
- エアコン除湿を使うときの設定温度
- 状況別、エアコンの最適な使用方法
- エアコン除湿の効果を高めるアイテム
除湿機能の最適な活用方法を知って、快適に日々を過ごせるようにしましょう。
知っておきたいエアコン除湿の基礎知識
エアコンの除湿機能を正しく使うために、まず知っておきたい基礎知識を紹介します。
お伝えするのは、次の3つです。
- 冷房と除湿の違い
- エアコン除湿と除湿器の違い
- 3種類の除湿機能の使い分け方
除湿と冷房の違い

夏に使うエアコンの機能といえば、除湿と冷房があります。
両方とも部屋を涼しくしてくれる点では同じですが、それぞれの主な使用目的は異なります。
湿気が気になる時期は除湿を使い、暑さが気になる時期は冷房を使うことがおすすめです。
- 室内の水分を含んだ空気を機械の中に取り込み、冷えた空気を室内に送る
- 室内の湿気を下げると同時に、室温をやや下げる
- 使用が向いている時期は、梅雨など湿気によるジメジメ感が目立つ時期
- 室内の暖かい空気を機械の中に取り込み、冷たい空気を室内に送り込む
- 室内を涼しくするが、除湿効果はない
- 使用が向いている時期は、真夏など気温の高さが気になる時期の使用
エアコン除湿と除湿器の違い

エアコンの除湿機能の代わりに、よく使われるのが除湿器です。
除湿器は、エアコンの除湿機能と同様、水分を含んだ空気を取り除くことで湿度を下げてくれる機械です。
しかし、エアコンのように室温を下げる効果はありません。
除湿器の種類によっては、機械の熱で室温が上がる場合もあります。
そのため、梅雨など暑さとジメジメ感が気になるときはエアコンを使い、夏以外で湿気が気になるときは除湿器を使うことがおすすめです。
| 除湿機能 | 冷房機能 | 通年利用 | |
| エアコン除湿 | ◎ | 〇 | × |
| 除湿器 | ◎ | × | 〇 |
3種類の除湿機能の使い分け方

エアコンの除湿機能は製品によって異なりますが、基本的に3つの種類に分けられます。
どのエアコンにも備わっているのが、一般的な除湿機能。
それに加えて、「再熱除湿」と「ハイブリット除湿」と呼ばれる機能があります。
| 温度 | 湿度 | 季節 | 目的 | |
| 除湿 | 〇 | ◎ | 梅雨・夏 | 湿気を下げる室温をやや下げる |
| 再熱除湿 | △ | ◎ | 梅雨 | 湿気を下げる室温が上がる可能性がある |
| ハイブリッド除湿 | 〇 | ◎ | 梅雨・夏 | 湿気を下げる室温は一定に保つ |
再熱除湿は、機械内で温めた空気を室内に送り出す機能のこと。そのため、除湿使用時の室内の冷えでお悩みの方に向いています。
ハイブリッド機能は、冷たい空気と暖かい空気を混ぜてから室内に送る機能のこと。一般的な除湿ほど冷えず、再熱除湿ほど暖かくないため、快適な室温を保ちたい方に向いています。
風向きや設定温度だけではなく、目的にあった除湿機能が備わった製品を選び、使用することが大切です。

エアコン除湿、正しい風向きは?

エアコン除湿の正しい風向きの設定方法は、室内環境や悩みによって異なります。
ここでは、次の3つの悩みに対する風向きの設定方法をお伝えします。
- 湿気が気になる
- 冷えが気になる
- 室内の温度を均一に保ちたい
【悩み1】湿気が気になる場合
梅雨などジメジメとした時期だけではなく、水辺の近くや日光が差し込みにくい場所など、湿気が溜まりやすい環境にお悩みの方は、エアコンの除湿機能の風向きを下向きに設定してください。
湿気を多く含んだ空気は、水分で重たくなっているため、下に溜まる傾向にあります。
そのため風向きも下に設定し、集中的に湿気が溜まっている場所の空気を循環させるようにしましよう。
【悩み2】冷えが気になる場合
エアコンの除湿機能を使うと、室内が冷えすぎてしまうという方は、風向きを上向き、もしくは水平に設定してください。
そうすることで、エアコンから送られてくる冷えた空気が、直接身体に当たることを防げます。
また、冷たい空気は室内の下部に溜まる傾向にあります。
風向きを水平よりも上に設定することで、冷たい空気が室内全体に行きわたるように工夫できます。
【悩み3】室内の温度を均一に保ちたい場合
立っているときは涼しいが、ソファに座ったりベッドに入ると、じわじわと暑さを感じるという経験をしたことはありませんか?
これは、冷たい空気は上に溜まり、暖かい空気は下に溜まる性質を持つためです。
室内での温度差を解消したい場合はスウィング機能を使って、上下両方に風が行きわたるようにしましょう。
そうすることで、室内全体に冷えた空気が行きわたりやすくなり、快適さがアップします。
エアコン除湿、正しい設定温度は?

エアコン除湿を効率的に使うために、風向きだけではなく設定温度も確認しましょう。
除湿機能を使うとき、もっとも望ましいとされる設定温度は26度から28度です。
これは、人が快適だと思える温度が28度だからです。
あまり暑さが気にならない時期や、部屋が狭くすぐに室温が下がる場合は、ひとまず28度に設定することがおすすめ。室内の冷えすぎを防ぐためです。
そのうえで、まだ暑さが気になる場合は、26度まで徐々に設定温度を下げて調整してください。
基本的には28度に設定し、長時間使用しても室内が冷えすぎないようにしましょう。
エアコン除湿が効かないとき、確認すべきこと
室内のジメジメ感や蒸し暑さが気になっているとき、エアコンの除湿機能を使ったのに室内の環境がなかなか改善されず、お困りの方は多いのではないでしょうか。
風向きや設定温度を変えてみても、解決できずお悩みの方もいるでしょう。
エアコン除湿の効果を感じられないときは、次の4つを確認するようにしましょう。
- フィルターの汚れ
- 室外機の汚れ
- エアコンの購入年
- 室内の環境
【確認1】フィルターの汚れ
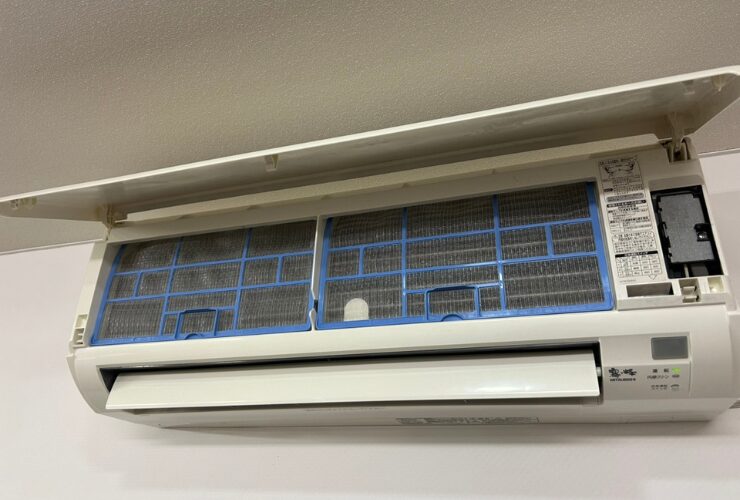
設定温度を下げても部屋の温度が十分に下がらない場合や、長時間運転しても湿気によるジメジメ感が解決されないときは、フィルターの汚れを確認してみてください。
エアコンのフィルターにほこりがついていると、除湿や冷房効率が下がってしまいます。
また、フィルターのチェックや掃除が抜けていると、知らないあいだにカビが繁殖してしまうことも。エアコン使用時にカビ胞子が室内にバラまかれ、衛生面や健康面に影響をおよぼします。
可能であれば2週間ごとに掃除をするようにしましょう。
掃除をする時間がない場合は、梅雨や冬の前などエアコンが活躍するシーズン前だけでも、手入れをしておくといいでしょう。
- 掃除機でフィルターのほこりを吸い取る
- 歯ブラシ等で網目に残ったほこりを取り除く
- 浴室や庭でフィルターの裏側から冷水をかけ、汚れを落とす
- 再度歯ブラシなどで残った汚れを取る
- 雑巾で水分をふき取る
- 陰干しでしっかりと乾かす
【確認2】室外機の汚れ

フィルターが清潔であっても、室外機が汚れていると、エアコンの効果が落ちてしまいます。
室外機はエアコンが取り込んだ暖かい空気を外に排出する役割を担います。
室外機が汚れていたり、排気口の前に物が置かれていたりすると、外に温かい空気を排出できなくなるため、エアコン使用時に十分な除湿・冷房効果が得られません。
室外機の近くに物を置いている場合は、移動させましょう。
室外機が土や落ち葉で汚れている場合は、次の手順で掃除してください。
- 外側の土や落ち葉をほうきで落とす
- プロペラカバーに溜まったゴミを歯ブラシなどで落とす
- 裏側や側面にある薄い金属板が汚れている場合は、優しく歯ブラシで落とす
- 水抜き穴の出口が詰まっている場合は細い棒やブラシで書き出す
【確認3】エアコンの購入年

エアコンの効果を十分に感じられないとき、そもそもエアコン自体が古い可能性があります。
エアコンの寿命は、一般的には10年といわれています。
それより長く使える場合もありますが、もって15~20年ほどでしょう。
エアコンの効きが悪いことに加え、次の異変が生じている場合は、買い替えを検討してみてください。
- 送風口から異臭がする
- 変な音がする
- 水漏れが発生する
- リモコンが効きづらい
- 漏電ブレーカーが落ちやすい
- 電気代が高くなった
【確認4】室内の環境

エアコンそのものに異常がなくても、室内の環境によっては除湿・冷房機能が十分に感じられない場合があります。
例えば、以下のような状態です。
- エアコンの能力に対して、部屋の面積が大きい
- 天井が高く、エアコンの風が部屋中に行きわたらない
- 家具が多く、エアコンの風が当たらない場所がある
- マンションの低層階や日当たりが悪いなど、湿気が溜まりやすい
こうした環境にお住まいの場合は、エアコン除湿だけでは十分に湿気対策を行えない場合があります。
しかし、湿気取りアイテムや電化製品を併用すれば、室内のジメジメとした環境は改善しやすくなります。

エアコン除湿の効果を高めるアイテム
「エアコンの除湿では十分に効果を感じられない」
「タンスの背面とかも、きちんと湿気やカビ対策をしたい」
という方には、湿気取りアイテムや電化製品の使用がおすすめです。
一概に湿気対策といっても、数万円するものから、身近なものを使ってゼロ円で使えるものまでさまざま。
お悩みや用途に合ったものを見つけられるよう、次の6つを紹介します。
- 扇風機
- サーキュレーター
- 除湿器
- 新聞紙
- 重曹
- 湿気取り剤
【アイテム1】扇風機

エアコン除湿では、十分に部屋が涼しくならないとお悩みの方は、扇風機を活用してみてください。
扇風機は風を送ることで清涼感を与えてくれますが、冷房のように室温を大幅に下げるわけではありません。
そのため、ジメジメ感と暑さは感じるがエアコンの冷房を使用するほどではないという時期には、エアコンの除湿機能と扇風機の併用がおすすめ。
エアコンの除湿機能で湿度を下げ、扇風機で室内を涼しくしましょう。
雨の日に室内干しをする方は、洗濯物に扇風機の風を当てておくことを、おすすめします。
そうすることで洗濯物を素早く乾かし、室内の湿度上昇や生乾き臭を防止しやすくなります。
【アイテム2】サーキュレーター
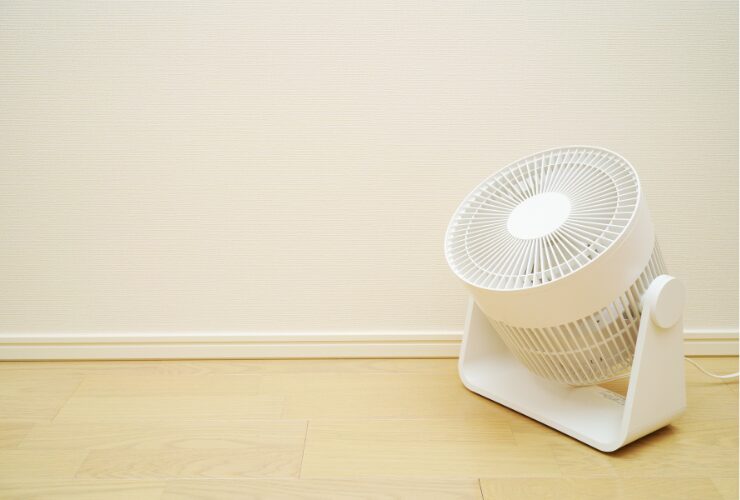
エアコン除湿を使ったときに、部屋の一部にしか風が当たらずお悩みの方は、サーキュレーターを併用してみてください。
サーキュレーターは扇風機と似ていますが、斜めや左右だけではなく、真上にも風を送ることができる点が特徴です。
これにより、サーキュレーターは空気を循環させ、室内に冷たい空気が行きわたるようにします。
サーキュレーターのおすすめの使い方は、エアコンの真下に置くこと。
そして風を斜め下もしくは水平に送るようにしましょう。
こうすることで、下部に溜まった爪痛い空気が押し出され、部屋全体に行きわたりやすくなります。
エアコンの風が壁など、どこか特定の場所に集中的に当たる場合は、その場所にサーキュレーターの風が送られるように配置してください。
【アイテム3】除湿器

エアコン除湿だけでは、湿気が十分に取り除けないと感じている方は、除湿器の使用を検討してみてください。
除湿器は、湿気を取り除くことに特化している製品です。
エアコンの除湿機能のような空気の冷却機能はありませんが、ジメジメ感の緩和やカビ対策が効率的になります。
次のようなお悩みを抱えている方は、除湿器の併用を検討してみましょう。
- 室内が広く、エアコンだけでは十分に除湿できない
- 室内干しをする機会が多い
- 室内干しをした際、乾きが遅く生乾き臭が発生しやすい
- 通年、湿気対策をしたい
除湿には効果的ですが、一方で電気代がかかるデメリットがあります。
節約をしたい方は、電化製品以外の湿気対策も検討してみてください。
【アイテム4】新聞紙
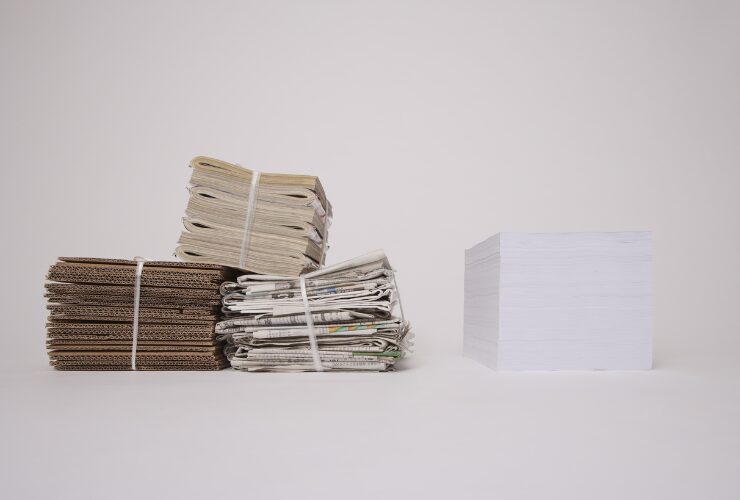
エアコン除湿だけでは、家具の背面など細かい場所の湿気対策ができないとお困りの方は新聞紙を活用してみてください。
新聞紙は、ほかの紙よりも水分を吸収しやすいうえ、脱臭効果もあります。
読み終わった新聞紙を、カーペットの下や家具の背面など、湿気が気になる箇所に置いておきましょう。
室内干しをする方は、新聞紙をいくつか丸めて、洗濯物の下に敷き詰めておきましょう。洗濯物の水分を吸収して、乾きを早めてくれます。
使用後は、新聞紙を天日干しして乾かせば、再利用もできます。
そのため、湿気対策にお金をかけたくない方におすすめ。
一方で、水分が溜まりすぎると、印字されているインクが漏れて床にうつる可能性があります。
そのため、できるだけこまめにチェックするようにしましょう。
【アイテム5】重曹

エアコンの風が届きにくいクローゼットや靴箱など、普段閉め切っている場所の湿気が気になる方は、重曹で手作り湿気取り剤を作ってみましょう。
重曹は脱臭効果があるため、靴箱など蒸れによる臭いが気いなる箇所には、特におすすめ。
必要な材料は、次の3つのみです。
- 室粉末状の重曹
- ジャムの空き瓶など、口の広い容器
- ガーゼなど空気が通りやすい布・紙
- 輪ゴム
重曹の湿気取り剤の作り方は、粉末状の重曹を容器に入れ、口にガーゼを被せて輪ゴムでとめるだけ。
気になる箇所にしばらく放置しておき、粉末が固まってきたら新しいものに変えてください。
固まった重曹は、そのまま掃除用洗剤としても活用できます。
重曹はアルカリ性のため、コゲや油汚れが気になるコンロやシンク、水垢や皮脂汚れが気になるお風呂場を掃除する際に使ってみてください。
【アイテム6】湿気取り剤

エアコン除湿では物足りないが、できるだけお金や手間をかけずに湿気対策をしたい方には、湿気取り剤がおすすめです。
湿気取り剤とは、置くだけで湿気を吸収してくれるアイテムのこと。
購入後は気になる箇所に置き、放置しておくだけで大丈夫。
湿気取り剤のなかには、半永久的に使用できるため買い替えが不要な商品もあります。
そのため、手作りをする手間やゴミの量、そして買い替える手間やお金が省けます。
1000円前後から、大きいサイズの湿気取り剤であっても2000円前後で購入可能。
新聞紙や重曹よりお金がかかるように思うかもしれませんが、長期間使えることを考えるとコスパのいいアイテムです。
エアコン除湿では物足りない方には、炭八がおすすめ!

エアコンを使うだけでは、除湿効果が十分に得られないと思う方や、通年除湿をしたい方は、炭八がおすすめ。
炭八の特徴は、針葉樹を原料としていること。その吸湿力は備長炭の約2倍です。
さらに、半永久的に使用できるため買い替える必要がありません。
使い方はとてもシンプルで、ベッドの近くやクローゼット内など、湿気が気になる箇所に置いて放置しておくだけです。
吸湿力が下がったと感じたときは、天気がいい日に天日干しをするだけで大丈夫。
炭のなかに溜まった湿気を吐き出し、吸湿力を取り戻してくれます。
「エアコンと電化製品の併用だと、電気代が気になる」
「湿気取りようのアイテムは手入れや買い替えが面倒くさい」
「だけど、しっかりと湿気を吸収してくれるアイテムがいい」
という方は、ぜひ炭八の使用を検討してみてください。

まとめ
今回は、エアコン除湿の風向きなど、効果的な使い方に悩む方に向けて、以下の項目をお伝えしました。
- エアコン除湿の基礎知識
- エアコン除湿を使うときの風向き
- エアコン除湿を使うときの設定温度
- 状況別、エアコンの最適な使用方法
- エアコン除湿の効果を高めるアイテム
エアコンの除湿機能は、お悩みや室内の環境に合わせた使い方をすることが大切。
また、電化製品や湿気取り剤といったアイテムと併用することで、より高い除湿効果が期待できます。
涼しくサラッとした空気を保ち、ご自宅で快適に過ごすための参考にしてみてください。
著者情報
最新の投稿
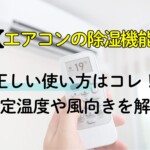 カビ2025年2月24日エアコンの除湿機能の正しい使い方はコレ!設定温度や風向きを解説
カビ2025年2月24日エアコンの除湿機能の正しい使い方はコレ!設定温度や風向きを解説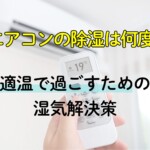 カビ2025年2月22日エアコンの除湿は何度に設定するべき?適温で過ごすための湿気解決策
カビ2025年2月22日エアコンの除湿は何度に設定するべき?適温で過ごすための湿気解決策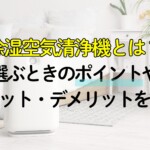 湿気2025年1月26日除湿空気清浄機とは?選ぶときのポイントやメリット・デメリットを紹介
湿気2025年1月26日除湿空気清浄機とは?選ぶときのポイントやメリット・デメリットを紹介 カビ2025年1月25日ペットボトルで除湿できる?電気代ゼロで効率的に除湿する方法を7つ紹介
カビ2025年1月25日ペットボトルで除湿できる?電気代ゼロで効率的に除湿する方法を7つ紹介




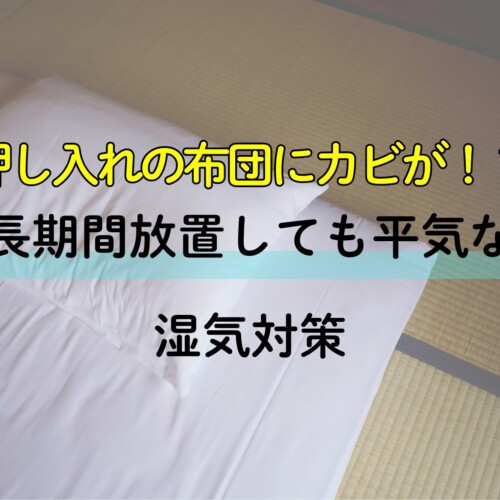
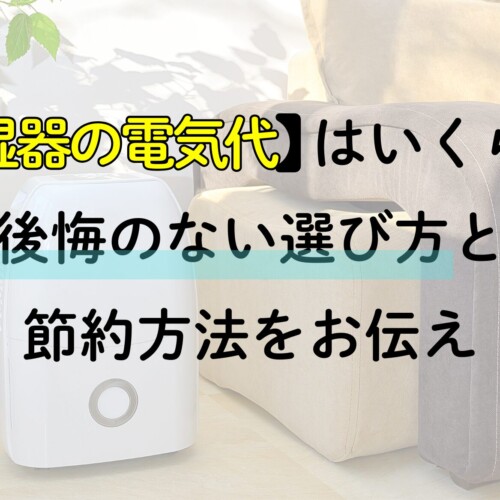




この記事へのコメントはありません。